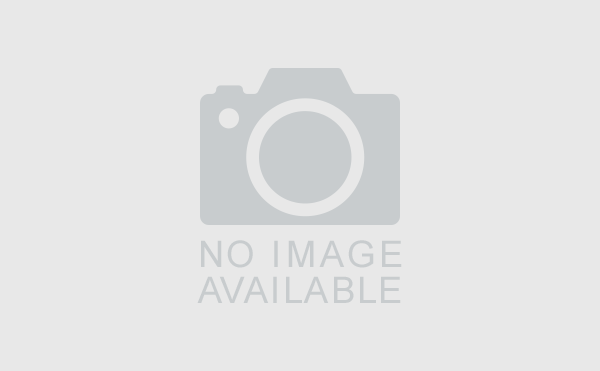髄液
髄液とは?
- 脳と脊髄を満たしている透明な液体で、医学的には「脳脊髄液(のうせきずいえき)」と呼ばれます。
- 主に脳室と言う空間で作られ、脳や脊髄のまわりを循環しています。
役割
- 保護クッション
脳や脊髄はとてもデリケート。髄液が「水の浮力」で守り、衝撃を和らげています。 - 循環と排出
脳の代謝で出た老廃物を流し、体に排出する働きがあります。いわば「脳の下水道」です。 - 環境の安定
脳や神経細胞に必要な栄養やイオンバランスを調整し、働きやすい環境をつくります。 - 神経伝達の促進
水(髄液)がある事で神経伝達(電気信号)がスムーズになり、末端部まで神経が伝達し、また、末端部からの情報が脳へしっかりと伝達出来ます。
面白いポイント
- 一日に3~4回入れ替わるほど循環が活発。
- 量は大人でおよそ120〜150ml程度。約500ml/日、脳で作られます。
- 最近の研究では「睡眠中に老廃物の除去が進む」ことも分かり、認知症予防との関連も注目されています。
脳脊髄液の循環
後頭骨と仙骨の動きがポンプとなり、頭頂部から背骨を通り、骨盤(仙骨)まで循環しています。
一般的な呼吸のリズム(肺が動く事で胸郭が動くので、それにより背骨が動く)でも循環はされますが、その動きとは異なる第一次呼吸システム(後頭骨と仙骨の動き)と呼ばれる動きによって6~12回/分、循環しています。
クラニオセイクラム(頭蓋仙骨療法)
クラニオセイクラムは(頭蓋仙骨療法)は、この6~12回のリズムを確認し、そのリズムを促進させるテクニックです。
脳脊髄液が頭蓋骨に及ぼす力は微細ですが、それを感じ取り、調整を行います。
このリズムは頭蓋骨や背骨、骨盤にのみ起こる動きではなく、全身でも確認する事が出来ます。
微細な動きなので、熟練した施術家から学ばないと気づけないほどの動きです。
人によっては、施術を受けている最中に、自発動が起こる事があります(勝手に手足が動き出す動き)。
https://youtube.com/shorts/x97EtQ9s5Uc?si=pn48K-ngSvQItwGu
これは身体に溜まっている不調(歪)を、身体が勝手に調整をかけている動きです。
沢山動けばそれだけ治そうとする力が強いと言う事で、動きが無ければ意識が覚醒状態にあるので、施術を受けている際にはあまり何かに集中させたり、考え事をしたりしない方が良いです。
ゆったりし、眠たければ寝ていただいて構いません。
クラニオセイクラムを受ける頻度は、『月に〇回がおススメ!』と言う事は提案していません。
しかし、髄液にしろ、体液にしろ、循環し続けている事は事実で、また、その循環に滞りは頻繁に起こっている事は事実です(現に、夕方に浮腫んだり、寝起きに浮腫む事って体感的にありますね?)。
これら滞りをしっかりと循環させ続ける事が、身体末端部まで神経をしっかりと流し、また、末端部からの情報をキチンと脳がキャッチ出来る身体となれば、健康で健やかで居れます。
気づいたら「○○出来なくなっていた」は、体液の滞りがあったせいで、神経伝達が弱くなっている証拠です。
それをずっと放ったらかしにした結果、脳細胞が活動を止め、その数が増えて行く事が”認知症”であると考えます。
脳細胞は必ず減ります。
年と共に必ず減ります。
耳を動かせない様に、足の指を手の指の様に動かせない様に、滞りを放ったらかしにする事で情報伝達は減り、いつしか脳細胞のその領域は小さくなり、委縮して行きます。
髄液の滞りにより、頭蓋内の圧が高まると水圧で脳細胞がヤラレます。
髄液も定期的に流しておく。
これはとても大事な事だと考えますので、クラニオセイクラムを受ける頻度はご自身で決めて下さい。