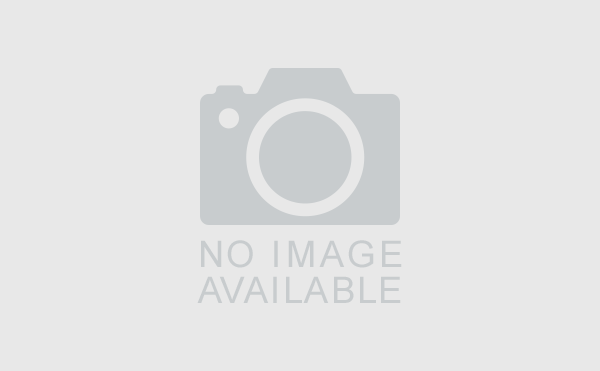足がツル
足がツルって話を最近はよく聞きます。
✅汗によりミネラルが抜けて行く
✅体内の水分不足
✅足の疲労の蓄積
✅筋力不足
これらが主な原因と考えられます。
そもそも人体には血液を通すシステムが存在し、それを「血管」と呼びます。
血管とは、血を通す管。
つまり、ホースです。
しかし、血管と毛細血管は別です。
血管は血液を通す管(ホース)ですが、毛細血管は全くの別物です。
毛細血管とは、”ザル”です。
ザルなので、大きなモノはそこから出ませんが、水は駄々洩れです。
つまり、赤血球などは血管内に残り、血しょうは流れ出ます。
血管から流れ出た血しょうの事を、組織液と呼びます。
組織液の中には酸素や栄養素を含み、それらが直接、細胞とやり取りを行います。
そうして代謝によって出た、老廃物は組織液の中に排出され、それが毛細血管の中に戻るシステムとなっています。
毛細血管の中に、アルブミンと言うたんぱく質が存在し、それが水を吸収するスポンジの役割をしています。
このアルブミンが不足すると(肝臓が壊れた状態)、毛細血管内に組織液が戻れず、細胞が水浸しの状態になります。
その水浸しの状態で有名なのが、痩せこけているのにお腹だけがプクッと出た状態、腹水です。
人体の中で、最も血液を欲ししている器官。
それが「脳」です。
心臓は血液を送り出す器官ですが、血液を回収するだけのパワーはありません。
先に言った様に、血管とはホースです。
毛細血管もホースであれば、血液は心臓の力だけで循環出来ます。
しかし、毛細血管は「ザル」だと書きました。
つまり、水が漏れているので、心臓の拍動で血液が心臓に戻る事はないのです。
なら、どうやって戻るのか??
一つは、血管の拍動です。
心臓から送り出された血液の圧により、血管は膨らみます。
心臓が広がるタイミングで血管にかかる圧は減るので、血管はへこみます。
この、膨らむ→へこむ→膨らむ→へこむ→膨らむ・・・の動きが心臓のポンプ同様の働きをし、静脈を動かします。
静脈は心臓から送り出される血圧が来ないので、弁が存在し、その弁のお陰で心臓へ心臓へと血液は戻って行けます。
次に、呼吸。
肺が膨らむ→へこむ→膨らむ→へこむ→膨らむ・・・これもポンプ作用をしているので、肺の動き(横隔膜の動き)で肋骨が動き、その動きで血管(静脈)も動かされ、血液が心臓へと送られる(内臓も動くので、その動きがポンプとなり静脈血は心臓へと運ばれる)。
次に、筋肉の動き。
筋肉の縮む→伸びる→縮む→伸びる→縮む・・・の動きによって、筋肉の中や皮膚の静脈は動かされ、血液は心臓へと戻されます。
特に下肢(下腿)は血液が溜まる場所(重力によって下に溜まる)。
足趾の動き、ふくらはぎの収縮は筋肉が動き、それによりポンプ作用が働き、下から上へと血液を押し上げます。
これが「第二の心臓」と言われる所以です。
足趾の動きが無ければ、血液が心臓に戻って行く事は弱くなります。
さきほど書いた様に、人体で最も血液を欲している器官は「脳」です。
血液が最も溜まる場所は、足です。
脚に血液が溜まり過ぎると、脳は酸欠・栄養不足となり、機能が乱れますので、そうさせない為に、血液を強制循環させようとします。
それが、「攣り」です。
また、血液がサラサラながれなくても脳は血液不足と判断し、強制的に収縮させます。
これが水分不足による攣るメカニズムです。
ミネラル不足は筋滑走の不良を引き起こします。
カルシウムは筋収縮に必要で、ナトリウムは細胞の振るえに必要です。
これらが乱れると攣りが起こります。
筋力不足は下から血液を押し上げるだけのパワーが無くなります。
しかし脳は血液不足と判断すると、攣りを起こさせ脳を守ります。
この様にして足がツル現象は起こります。
足をどうやったら攣らない様に出来るか?
それは、水をしっかりと飲み潤わせ、ミネラルを補給し、歩く・足指を動かすなどして筋力を鍛え、下に溜まった血液を押し上げる必要があると言う事です。