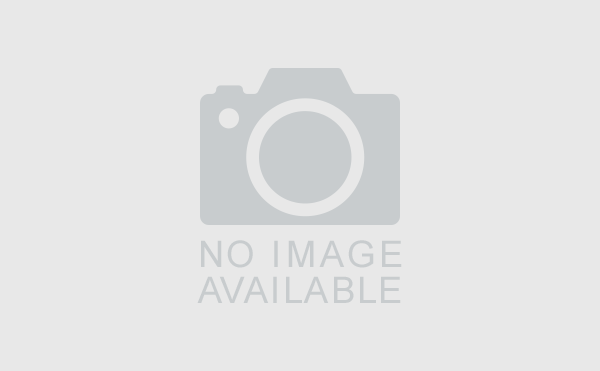腰を捻る動きとは
体幹を捻る時、多くの人は「腰を回している」と感じています。
が、実は腰はほとんど回っていません。
体幹の回旋は、股関節と胸椎によって生み出されており、その構造を理解するだけで、体の使い方もケガの予防も大きく変わります。
体幹回旋の可動域は70〜90度ほどですが、その内訳を深く見ていくと、身体の本質が見えてきます。
胸郭(肋骨・胸骨・胸椎)は、かご状になっているのでそもそも可動性は少ないです。
12個存在する胸椎は、全体で30〜35度回旋するとされ、特にT5〜T8の中部胸椎が6〜8度と最も動くとされます。
ここが体幹回旋の中心となります。
上部胸椎は4〜7度、下部胸椎は2〜3度と徐々に小さくなっていきます。
多くの人が腰を捻っていると思っている腰椎は、全体でわずか5〜10度。
椎間関節の構造上、そもそも回旋出来ない作りになっており、ここで無理にひねると関節や椎間板を痛めるリスクが高まります。
それでも僕らは大きく捻れると思っている。
その答えは、股関節にあるのです。
股関節部分は体幹回旋時に10〜15度ほど回旋し、さらに股関節の内旋・外旋が加わることで、片側30〜45度近くの動きを作ります。
つまり「体幹を捻る」動きとは、胸椎+股関節であり、特に股関節がほぼメインとなっていると言う事です。
実際に右にひねる場合、胸椎30度、骨盤15度、股関節20〜30度ずつ回旋しています。
この分配こそが、体の合理的な設計です。
ここで重要なのは、胸椎や股関節が硬い人は、足りない回旋を腰で補おうとすること。
これにより慢性的な腰痛、ヘルニアなどの椎間関節の炎症、損傷を引き起こします。
さらに細かく見ると、胸椎の中でもT5〜T8が最も動くため、ここを解放するだけで回旋力は劇的に変わります。
股関節では、内旋制限があると骨盤が逃げず、外旋が硬いと回り始めが詰まります。
そして片脚立位では、支軸側の股関節内旋が鍵となり、回転スポーツ(ゴルフ、野球)ではここがパフォーマンスの決定因子になります。
結局、体幹回旋は「どこで回すか」が本質であり「どれくらい回せるか」よりも「どの関節がどれだけ分担できているか」が重要です。
腰痛で悩まれている方の多くが腰の問題と思われていますが、腰の問題よりも股関節の問題であり、中部胸椎の問題です。
もっと言うと、中部胸椎の問題は胃の反射や精神的・思考的要因によって左右されるので、運動不足・柔軟性の問題ではない事の方が多いです。
そうして何より、股関節の問題は、骨アライメント、つまり、足部の偏平足・巻き爪・外反母趾・魚の目・タコ・ハイアーチ・指でゲンコツが出来ないなどが原因で不正になり、それが結果としてスネ・膝・大腿へと上がり、股関節の動きを狂わせ、股関節を動かす筋肉のバランスを崩させる事から起こっています。
ここで何が言いたいかと言うと、腰痛は腰に問題があるのではなく、股関節の動き制限であり、それは足部のアライメント不正から起こっていると言う事です。
それらを調整・トレーニングする事が大事だと言う事です。