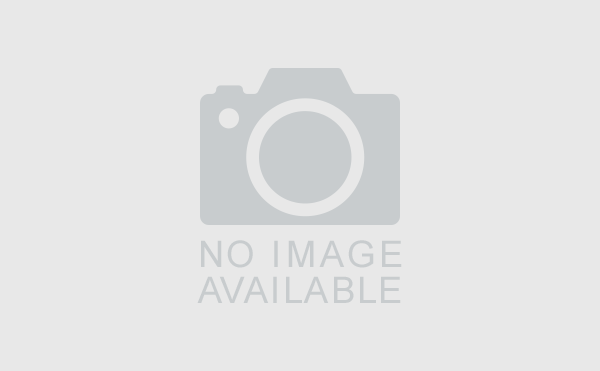背部痛(寝違い様)…その正体は?
首をちょっと動かしただけで「ビキッ」と背中に走る激痛。
このような背部痛(寝違い様)は、原因が一つではありません。
それぞれの原因を見極めるためには、視診・触診・動診・知覚検査など、複数の検査を組み合わせる必要があります。
■ 背部痛の主な原因とは?
背部痛といっても、以下のように原因は多岐にわたります:
- 骨格系由来(胸郭の歪み・関節のフィクセーション)
→ 視診や触診で異常な歪みや可動性の低下が確認できます。 - 筋由来(斜角筋・僧帽筋・肩甲挙筋などの過緊張)
→ 触診により、緊張の強い部位や圧痛点を丁寧に探ります。 - 神経由来(腕神経叢・脊髄神経根の影響)
→ 知覚異常や放散痛の有無、動きによる変化から判断します。 - 頸椎由来(椎間関節・椎間板の機能不全)
→ 頸部の動診により、特定方向での痛みや可動制限を評価します。
■ 鑑別のために「検査」が必要な理由
原因が複雑に絡む背部痛では、「これさえやればOK」という手技は存在しません。
大切なのは、症状の背景にある構造・機能・神経の異常を見抜くことです。
特に、神経由来の場合は、頸椎や胸郭の深部での圧迫や滑走不良が隠れていることもあります。
触診と動診、さらに知覚検査まで行うことで、全体像がようやく見えてきます。
■ 危険なサインを見逃さない
まれに「危険信号」が見られる場合があります。
- 吐き気やめまい
- 発熱や冷や汗
- 骨を押すと強い痛みがある
このような場合は、骨折や内臓疾患の可能性を考慮し、速やかに病院での検査を勧めます。
■ 検査を“施術の中に溶け込ませる”工夫
限られた施術時間の中で、いかに多くの情報を得て、冷静に判断するか。
その鍵は、検査を自然に手技に組み込むことです。
施術と検査の融合により、より精度の高い施術と、患者への安心感の両方が生まれます。
背部痛と一言でいっても、原因は千差万別。
視診・触診・動診・知覚検査のすべてが重要です。
そして、施術の中でそれらを自然に組み込むことで、施術者自身も落ち着いて判断とアプローチができるようになります。
原因を見極める目と、冷静に判断する術を持つことが、プロフェッショナルとしての信頼に繋がります。