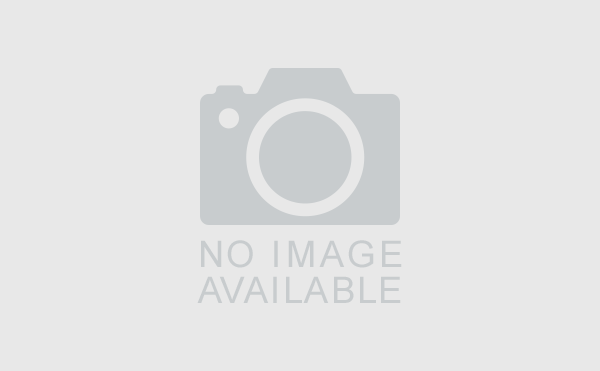水が溜まる
よく「膝に水が溜まった」とか、「水を抜くと癖になる」とか聞くと思います。
そもそも関節は、袋に包まれていて(関節包)、その袋には水が存在します(滑液)。
その水は、骨(軟骨部)に潤いを与え、養分を与え、滑りを良くする為のモノです。
この水が無ければ、軟骨同士がブツかり、栄養も来ないので軟骨が擦れてボロボロになるって事になります。
軟骨には血管が無いので修復出来ません(軟骨ではなく骨本体部分は、破骨細胞・骨芽細胞があるので骨折しても治るし、そもそも骨は2~5年で新しいモノへと作り変えられています)。
軟骨は、一度、壊れると壊れたままとなり、それはドンドン酷くなる可能性が高いです。
こうした壊れた部分が、関節を動かすたびに擦れ、熱を持ってきます(炎症)
この炎を消す為に、水で冷やします(これが”水が溜まる”原因で、抜いたところで炎症が治らないので水は溜まり続けます)。
どの関節にも水はありますが、特に下肢部では、上半身の体重と、床からの反力で相当強い圧力が関節部には常に掛かっています。
足部(脚ではない)は、外反母趾・魚の目・タコ・開帳足・偏平足・巻き爪・内反小趾などにより足の形が変わります(筋力不足・神経伝達不足)。
これらにより足の形が変わると、距骨(足首の骨)と脛骨(スネの骨)との位置関係が狂ってきます。
高齢女性に多く見受けられる、外くるぶしが大きく膨らんでいる現象は、外くるぶしに水が溜まっている状態です。
また、その足首バランスの崩れは、スネの骨と大ももの骨との位置関係を狂わせます(O脚、X脚)。
このO脚、X脚で膝を動かす事で軟骨部分にブツかり(本来、膝関節は蝶番の動きだけでなく、捻りと前後への滑り運動によって動いているが、これのどれかが極端に動いたり・動かなかったりする)、これにより膝部で炎症が起こり、膝に水が溜まる現象が起こります。
先にも書いた様に、下肢には相当強い圧力が掛かっている上に、膝は大きな関節なので袋も大きい。
そこで炎症が起こると、水も大量になるので抜く量も必然的に多くなります。
あと、骨盤部ですが、股関節にもそうした現象が起こり、それで股関節の変形も起こるのだと思いますが、股関節の場合は外表から直接触れないので(お尻の筋肉が厚いのと、脂肪組織が多い)関節に水が溜まっているのは判別出来ません。
しかし、骨盤部(仙腸関節部分)はよく分かり、骨盤の捻じれ(=背骨の捻じれ=身体の歪み=足の崩れ)があると仙腸関節部に水が溜まります。
仙腸関節は不動関節とも言われるくらいほぼ動かない関節です。
そこに水が溜まると言う事は、よほどの捻じれがある事を教えてくれ、且つ、グラついている事を意味するので、動かないモノが動くので痛みを伴います(いわゆる、腰痛)。
ここに出来る浮腫(水が溜まってグニュグニュとしてグミ状のモノが出来る)は、歪みが整うと無くなります(腰痛も無くなります)
その昔、「指を鳴らすと関節が太くなる」と言うのを聞いた事がある人も居られるかもしれません。
これは上記の事で説明がつく様に、骨が鳴る=相当強い圧力が関節部に掛かるので、軟骨破壊が起き、結果、炎症により水が溜まると言うメカニズムです。
ちなみに骨が鳴っているのは骨同士がブツかっている音ではなく、滑液中に溶け込んでいる窒素が、圧力によって高められ、それが圧力の低い方に移動する際に気泡化し弾ける時に発生する音です。
そのエネルギ-が相当強く、このエネルギーによって軟骨が破壊されると言う事です。
膝も本来の転がり滑り運動が出来ている時にはそのエネルギー発生現象は少ないですが、スネと太もものバランスが崩れた際には、左右・前後・斜めの圧力バランスが狂う事によって窒素が弾け、膝軟骨を破壊させ続け、それにより変形していくと言う訳です。
水が溜まるのは膝だけでなく、どこでも溜まりますが、特に下肢は上半身の重力と、床反力によって更に強く関節には掛かっている事。
バランスが崩れやすい事(筋力不足・神経伝達不足)。
重力によって、下(下肢)に血が溜まりやすい事(水が溜まりやすい環境下にあると言う事)。
お尻(股関節)は筋肉・脂肪によって目立たない。
これらによって膝が一番目立つと言う事になります。