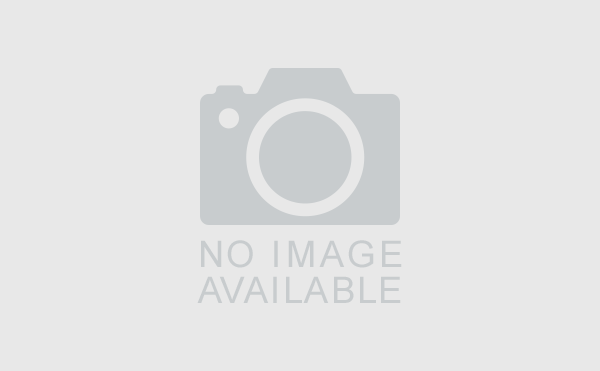情動の生理学
先ほど、アメブロの方に背景を知ると言うブログを書きましたが、その流れで、メカニズム的なブログを見つけ、まとめたのでシェアします。
■ 感情は「心」ではなく「身体」で生まれる
感情というと「心の中の出来事」と思われがちですが、
実際にはその多くが内臓の変化を脳が知覚した結果として生まれています。
怒りで心拍が上がる、不安で胃が痛む、悲しみで胸が締めつけられる──
これらは、身体が先に反応し、脳がその変化を“気持ち”として認識した現象です。
心理学者ウィリアム・ジェームズは言いました。
「われわれは泣くから悲しいのではなく、泣くという身体反応を感じ取って“悲しい”と知るのだ。」
■ 感情とは身体からの“信号”
感情(emotion)の語源は「動かす(emovere)」。
外界から刺激を受けると、まず内臓が動き、それを脳が感じ取ります。
つまり、感情とは身体の反応を知覚したものなのです。
- 恐怖:心拍上昇、胃の収縮(交感神経)
- 不安:胃酸分泌や腸の動きが乱れる(迷走神経)
- 怒り:血圧上昇、糖代謝の促進(副腎・肝臓)
- 悲しみ:呼吸が浅くなる(肺・迷走神経)
- 安堵・愛:心拍が落ち着き、消化が進む(副交感神経・オキシトシン)
■ 腸は「第二の脳」
腸には約1億個もの神経細胞があり、脳とは独立して働くことができます。
しかも、腸→脳への情報伝達の方が多い。
腸の状態がそのまま感情の基盤を形づくっているのです。
腸が乱れると不安や落ち込みが強まり、
腸が整うと自然と安心感が生まれる。
これは比喩ではなく、迷走神経を介した神経反射の結果です。
■ 感情と内臓の対応関係
- 心臓:緊張・興奮・愛
- 胃:不安・心配
- 肝臓:怒り・苛立ち
- 腸:恐れ・警戒・直感
- 肺:悲しみ・喪失感
感情とは、これら内臓の変化を脳が「意味づけ」したもの。
“心で感じる”というより、“身体の奥で感じている”のです。
■ 感情のスイッチを操る自律神経
感情を動かす主役は自律神経系です。
交感神経(アクセル)と副交感神経(ブレーキ)のバランスが、
一瞬で入れ替わることで“気分”が生まれます。
つまり、感情とは神経電流のゆらぎを体験している状態なのです。
■ 進化の中で育まれた情動
感情は、生き延びるための内臓反射が進化した結果として発達しました。
- 魚類:逃避反射(恐怖の原型)
- 両生類:緊張・固まる反応
- 哺乳類:愛・不安などの社会的情動
- 人類:共感・慈愛・倫理的感情
つまり感情とは、生命が内臓を通して磨いてきた“知恵”。
私たちは今も、太古の身体のリズムを生きているのです。
■ 腸が「心」をつくる
体内セロトニンの約90%は腸で作られています。
腸内環境が悪化すると、セロトニン伝達が乱れ、
不安・焦燥・落ち込みが強まります。
「気分の波」は腸から始まる。
心を整えたいなら、まず腸を整える。
これが“腸脳相関”の本質です。
■ 感情を整えるには、内臓を整える
思考で感情を抑え込むより、身体を整える方が早く確実です。
- 深呼吸する → 心拍と呼吸のリズムが整う
- お腹を温める → 副交感神経が優位になる
- よく噛んで食べる → 胃腸が安定し、迷走神経が整う
- 軽く動く → 血流と内臓リズムが活性化する
感情を変えたければ、身体を変える。
身体の調律が、心の安定をつくるのです。
■ 結論:心身一如は生理学的な事実
感情とは、脳だけでなく内臓・神経・ホルモンの総合的な反応です。
脳はその変化を「物語」として解釈しているにすぎません。
だからこそ、感情を理解するとは、
自分の身体の声を聴くことでもあるのです。
頭で整理するより、まず感じてみる。
そこにこそ、本当の“心”が息づいている。
感情とは、生命が自らのリズムを感じ取る力。
それは、心と身体がまだ分かれていなかった頃の“記憶”である。