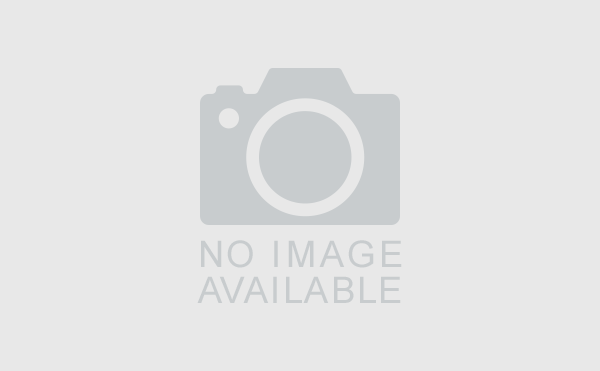あくびちゃんとバタフライ
あくびが出る瞬間。
それは、ほんの一瞬、心と身体が「脱力」に向かう。
けれど、あくびはただの眠気の合図ではない。
もっと奥深い、身体の“中心”に働きかける、極めて本能的な調整の動きだ。
『蝶形骨』
頭蓋骨のほぼ中央、ちょうど脳の底面あたりに位置するこの骨は、蝶が羽を広げたような形をしている。
ここは、前頭骨、側頭骨、後頭骨、そして顔面骨と連結し、脳を下から支える“要石”のような存在。
この蝶形骨の中央には、「トルコ鞍」と呼ばれるくぼみがあって、内分泌の司令塔である“下垂体”が収まっている。
つまり、蝶形骨がわずかにでも捻れたり、圧迫を受けたりすれば、視覚・嗅覚・ホルモン・自律神経・顎関節など、全身に波紋のように影響が広がってしまう。
そしてこの蝶形骨、あくびの動作と深く関わっている。
大きく口を開け、喉を広げ、顎を下げ、呼吸を深く吸い込む。
あくびの一連の動きは、顎関節のリリース、側頭筋・咬筋・翼突筋の弛緩を誘発し、その連動で蝶形骨にわずかな“ゆらぎ”が生まれる。
まるで閉じていた蝶の羽が、そっと開くように。
この微細な動きこそが、頭蓋全体の圧力バランスを調え、脳脊髄液の循環を促す鍵になる。
特に、交感神経優位でガチガチになった時や精神が張りつめている時に出るあくびは、「副交感神経へのシフト」を示している。
脳を休ませる準備に入るスイッチだ。
整体の現場でも、施術中あるいは施術後にあくびが出始める瞬間がある。
それは、身体が“今ここ”に戻り始めた証。
蝶形骨を中心とした頭蓋の微細な動きが回復し、呼吸のリズムが深まり、硬膜の緊張がほどける。
この変化が自然とあくびを誘い、あくびがさらに整える。
まさに好循環。
人は無意識のうちに、自分を整える術を知っている。
あくびはその最たるものだ。
「眠くないのにあくびが出る」
そんなときこそ、蝶形骨が何かを求めているのかもしれません。