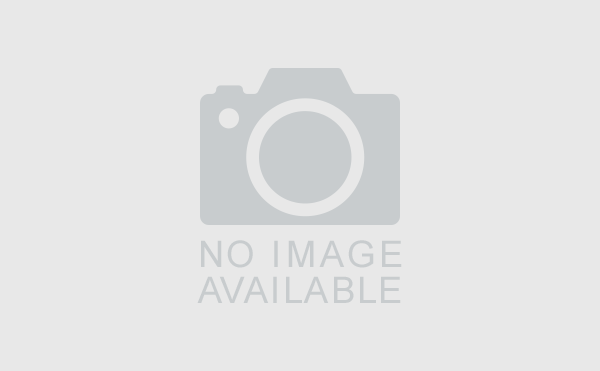「骨で立つ」事の本当の意味
~力まず、歪まず、生きるための身体の使い方~
「ちゃんと立って下さい」と言われると、あなたはどこに力を入れますか?
肩に力が入り、膝を突っ張り、お腹を引っ込め、背筋をピンと張る・・・
そんな「頑張って立つ姿勢」をとっていないでしょうか?
でもそれは、本来の“自然な立ち方”ではありません。
むしろ、疲れやすく、痛みを呼び、呼吸さえ浅くなる立ち方です。
では、どう立つのが正解か?
それが、「骨で立つ」という考え方です。
■ 骨で立つとは?
文字通り「骨格の構造を活かして、筋肉の無駄な緊張に頼らずに立つ」事です。
もっと具体的にいえば、
- 骨盤の上に背骨を乗せ
- 頭蓋骨がまっすぐ積み木のように乗り
- 脚の骨が柱として体を支える
こういった骨同士の自然な連携によって、最小限の力で立つ状態が「骨で立つ」と言う事なのです。
■ なぜ骨で立つことが重要なのか?
1. 無駄な力が抜ける(=副交感神経が優位になる)
骨がキチンと立つ。
つまり、下の骨の上に骨がちゃんと並ぶと、筋肉は休む事が出来ます。
骨が並んで立ってないと骨のバランスを保つ為に筋肉に無駄な力が入ります。
すると、筋肉に力を入れ続けさせる為に交感神経が優位になり、それ故に脱力が出来なくなり肩こり・不眠・呼吸の浅さなどの症状が起こって来ます。
骨で立つと、筋力が最小限で済むため、全身が“オフモード”になりやすいのです。
2. 身体の歪みが減る
筋力に頼った立ち方は、左右差・癖・負担のかかる部位を作り出します。
骨で立つと、重力が「まっすぐ」通るため、歪みにくく、疲れにくい構造になります。
3. 内臓が正しい位置。に戻る
猫背・反り腰・お腹の力み……これらは内臓の位置を下げ、消化や代謝にも影響を与えます。
骨で立つ事で、内臓は“吊るされた位置”に戻り、内臓機能が回復していきます。
4. 感情が安定する
意外に思われるかもしれませんが、立ち姿は「心の姿勢」でもあります。
骨で立つ事で、呼吸が深くなり、脳の酸素供給が改善し、自律神経も整い、感情も穏やかになります。
■ どうすれば骨で立てるのか?
以下は、ご自宅でできる簡単なワークです:
🧘♂️ 骨で立つための3ステップ
- 足裏で床を感じる
かかと・小指球・親指球の3点で体重を支えてみましょう。 - 骨盤を立てる
仙骨がまっすぐ立つと、その上に背骨が乗っていきます。 - 力まずに立つ
「頭のてっぺんを糸で吊られている」ようなイメージで、背骨を上へ伸ばします。胸を張らず、力を抜くのがコツです。
呼吸が深く、静かに出来るなら、正しく立てている証拠です。
変形性○○や、しょっ中、ぎっくり腰になる、肩が凝りやすいなど多くは骨で立てていません。
筋肉を無駄に力ませ、骨に負担を掛けています(故に変形する)。
骨で立つ事が出来る様になると、筋力に使っていた無駄なエネルギーは別の事に回せます。
心の安定もそうですが、気持ちに余裕が生まれるので運気も上がります。
骨で立ててるかどうかをチェックする簡単な方法は、片足立ちです。
年齢と共に脳も老化してきますので、歳と共に片足バランスは難しくなってきますが、それでも骨がキチンと立てていると片足バランスも長時間出来ます。
上記に何処を意識するか?書きましたが、それよりも簡単なのは片足で立てるかどうか?バランスが保てるかどうか?
肩こり腰痛でなやんでおられるなら、おそらく片足立ちも難しい筈です。